蔦重が生まれ育った「吉原」の歴史
蔦重をめぐる人物とキーワード①
■移転、隆盛、衰退と時代の波に翻弄されていた吉原
1590(天正18)年に徳川家康が入府したことにより、江戸は急速に発展した。旗本や御家人、労働者らが全国から流入し、人口が爆発的に増加。都市の発達とともに江戸に遊女屋が発生したのは、上方や駿河で遊女屋を営んでいた者らが、発展を遂げる江戸で一旗揚げようとしたことも関係している。当時の江戸の男女比率は男性が6割ほどと多く、そこに商機を見出したらしい。遊女屋の営業について、家康も半ば放任するような発言も残している(『事跡合考』)。
そんななか、1612(慶長17)年に庄司甚右衛門(しょうじじんえもん)が、幕府に遊郭の設置を申請。これを受け、1618(元和4)年に2代将軍・徳川秀忠(ひでただ)の治世において、公許の遊郭としてスタートしたのが「吉原」である(前年に開始されたとする説もある)。
開業が許可された場所は「葦屋町之下」で、現在の東京都中央区日本橋人形町付近だった。葭(よし)や葦(あし)が生い茂った湿地帯だったことから、この地は「葭原」と呼ばれており、後に縁起のいい「吉」の字を用いた「吉原」に改称されたという。
江戸の発展がますます盛んになると、吉原周辺にも人家が急増する。吉原開業から約40年が経った1656(明暦2)年、風紀の乱れや治安の悪化を懸念した幕府は吉原に対し、移転を持ちかけた。
代替地として幕府が提案したのが、江戸の中心地から離れた、台東区千束(せんぞく)だった。当時は田畑の広がる寂しく辺鄙(へんぴ)な土地だったようで、反発する声を想定した幕府はいくつかの条件を提示している。町割りを5割程度増やす、1万500両の移転代金を負担する、などである。
こうして、およそ2万坪という敷地に、新たな吉原が建設された。敷地の周囲は遊女の逃亡を防ぐためにお歯黒どぶと呼ばれる堀が張り巡らされ、原則的に唯一の出入り口となった大門が設置された。常駐の番人が配置されるなど、厳しい監視下のもと、吉原は再開した。なお、移転前の吉原を「元吉原」、移転後の吉原を「新吉原」という。
不便な場所だったにもかかわらず、新吉原には多くの客が詰めかけ、大繁盛となった。元吉原では禁止されていた夜間営業が認められたことや、元禄年間(1688〜1704年)の好景気などが相まって、身分の高い武士や豪商らがこぞって豪遊をしに訪れるようになったからだ。富裕層相手の商売として繁栄する吉原には、次第に格式や伝統が確立されていった。

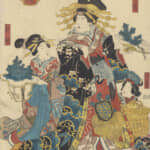
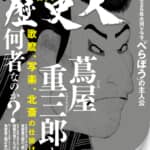
_電子透かしあり-150x150.jpg)


